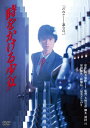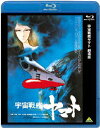UnsplashのCallum Skeltonが撮影した写真

2023年(第95回)アカデミー賞にて。作品賞をはじめとする主要6部門を含む計7部門で受賞の快挙!!
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』の感想と、本作の関連情報についてのまとめの記事です。

ポイント
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する勝手な感想文
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する音楽情報
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関するにパンフレットの記憶

本記事の信憑性
特に映画通でもなんでもない
映画鑑賞暦40年以上!?
CD1000枚以上コレクション
音楽大好きの技術系サラリーマンオヤジ(Robert)による
既鑑賞作品に関する感想について備忘録も兼ねてご紹介!
この記事を読んで
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』鑑賞してみようかな?
と思って頂ければオヤジ(Robert)幸せです。
(注意)
以下、ネタバレの可能性もありますのでご注意下さい!!
*本ページはプロモーションが含まれています。
▼ 提供:株式会社DMM.com証券 ▼
バナーのみ
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する勝手な感想文
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
通称”エブエブ”が、先日(2023年3月16日)開催された
2023年(第95回)アカデミー賞にて作品賞をはじめとする主要6部門を含む計7部門で受賞しました。
本年度アカデミー賞受賞 エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス 『This Is A Life』MusicClip


果たしてこのエブエブは何がそんなに凄いのか?
この記事を書くために、今回は変な期待をもってしまったり、
先入観が入ると冷静に観れない可能性があると勝手に思ったため
何とかアカデミー賞授賞式前に、極力前情報を入れないようにして鑑賞にのぞんだのですが
・・・
第一印象としては
鑑賞中にストーリーだけ追って終わってしまって、後に何も残らなかった作品
という感想でした。
1回目の鑑賞で感動できなかった3つの理由
繰り返しになりますが
今回の1回目の鑑賞は、沢山の情報により混乱の中で不完全燃焼のなかで終わってしまった😖という印象ですので
久々にそのモヤモヤを晴らすために、このブログの記事を書きながら
オヤジ(Robert)なりに、”感動できなかった理由”について少し整理してみました。
“最先端のカオス”についていけなかった
本作品は、物語の中盤から「多元宇宙(マルチバース)」という
別次元の自分から能力を借りて、現実の自分を表現できる
という世界で繰り広げられることになるのですが
その世界が、仮の世界といえども今一つ理解がおいつかず
バカバカしければバカバカしいほど、それがパワーとなって
ジャンプをより確実に成功させるという「バース・ジャンプ」も
映画『時をかける少女』で登場したタイムリープや、
アニメの宇宙戦艦ヤマトで登場したワープとも違う概念みたいだし
・・・と途中モヤモヤが増えてくると
置き去りにされた感😕がありながら鑑賞することになり
もはや石が登場するところは、何となく表現したいことは理解できるものの
正直気持ちも少し引き気味😑になっておりました。
また、数多くの人生の選択肢を表現するために使用されていた
100に近いカットの激速の切り替えのシーンなども
やらんとしていることは何となく分からんでもなかったのですが
こちらもモヤモヤがたまり完全にこの作品の世界でもある
“最先端のカオス”についていけなかった感じ😰でした。
そもそもオヤジ(Robert)が、アメリカ的ギャグセンスを理解してない
それから、バカバカしければバカバカしいほど、それがパワーとなって
ジャンプをより成功させるという「バース・ジャンプ」
を実現するために行う、”数々のバカバカしいこと”のクダラナイ感じも
オヤジ(Robert)がそのアメリカ的ギャグセンスを理解してないためか
残念ながら今ひとつ心に刺さるものが無く😑
ベーグルも
ホットドックの指も
やらんとしていることは分からんでもなかったのですが、これまたかえってモヤモヤがたまってしまった感じ😖でした。
ワクワクが少なかった印象のカンフーアクション
さらに、以下のWebの情報から
キー・ホイ・クァンの起用は何故? ダニエルズ、カオスな映画に込めた真摯な思い
出典:映画.com URL:https://eiga.com/movie/96942/interview/
もともと本作には、ジャッキー・チェンをキャスティングする
という構想があったようですので
ストーリーのなかで、カンフ-アクションのシーンは構想内だったと思われますが
その話題のカンフ-アクションが
ジャッキー・チェンの作品を観て育ったオヤジ(Robert)にとっては
テンポもゆるめで、ユーモアなどを感じられたのも印象的だったのは、一部ボカシ😅があるシーンくらい
意外性含めて、いまひとつワクワクする部分が少なかった感じ😑でした。
作品への理解がすすむ”ニヒリズム(虚無主義)”に関する解釈
ここまでの記事の内容から、オヤジ(Robert)的には正直今回は記事にするか?も微妙な作品だったのですが
パンフレットにあるコラムで話題にしていた内容のなかで
ニヒリズム(虚無主義)という考えかたが、今回の作品のテーマのひとつとして話題にされてたことにより
Web上の以下の記事などの情報から、広い観点でエブエブを理解できるようになり少し興味が出はじめました。
ニヒリズム(虚無主義)とは? ニヒリストって? 簡単にわかりやすく解説
ニヒリズム(虚無主義)とは?
この記事にて、ニヒリズム(虚無主義)という言葉の意味について以下のように要約されてますが
「物事の意義や価値は存在しない、自分自身の存在を含めてすべてが無価値だ」ということです。
これは、正に本作で悪役として登場する
”ジョブ・トゥパギ”の思想として活用されていたものであります。
さらに、この記事にもある”ニーチェとニヒリズムの関係”や、
宮崎アニメの『風の谷のナウシカ』を例に開設されている内容などについてを読み進めると・・・
ナウシカが消極的ニヒリズムから積極的ニヒリズムに至るまでの過程を描いた物語だからです。
ニヒリズム(虚無主義)という考え方に関して、理解が進んでくると同時に
ニヒリズム(虚無主義)というkeywordを中心に本作の構成を回想すると
作品のなかで登場する様々なシーンの意味についても見晴らしが良くなりました。
本作は、さきほどご紹介した以下の記事によると
キー・ホイ・クァンの起用は何故? ダニエルズ、カオスな映画に込めた真摯な思い
出典:映画.com URL:https://eiga.com/movie/96942/interview/
監督がもともと幼少の頃からニヒリズムのようなもので悩まれ
それを克服したことが背景にあるようですので
今回のアカデミー賞での快挙は
病んだアメリカ人の心に強烈に刺さったためとも言えると感じます。
また、この作品のラストで語られる不偏的なメッセージは
あらゆる思想をもつ人々に伝わり
日本の若い人の中でも本作により救われた人もいるのではないでしょうか。
素直に感度した受賞式
さらに、今回の作品の主役どころに抜擢された
ミシェール・ヨー
キー・ホイ・クァン
ジェームズ・ホン
という、アジアにルーツを持つ俳優たちについて
以下のJimmy Kimmel Liveでのインタビュー映像などから
彼らのポジティブオーラにより元気も頂き
James Hong on Working with Groucho Marx, Everything Everywhere All at Once & Getting His Star
Michelle Yeoh on Fighting, Having Hot Dog Fingers & Being Proud to Play a Superhero in New Movie
Ke Huy Quan on Steven Spielberg Audition for Indiana Jones, Being in The Goonies & Return to Acting
少しだけですが、彼らに関する理解が進んだ状態で
今回のアカデミー賞の授賞式を(WOWOWで放映したものを録画で)鑑賞しました。
授賞式では、当初の予想通りにてエブエブがほぼ主要部門を総ナメ状態でしたが
オヤジ(Robert)的には、作品としての受賞よりも
彼ら役者としての受賞に素直に感動しました。
特にキー・ホイ・クァンによる以下の受賞スピーチでのご自身の快挙を
「This is the American Dream!this is an Americandream!(これぞアメリカンドリームだ!)」
とのべられたシーンや
Ke Huy Quan is overcome with emotion as he accepts Oscar - full speech
映画『レイダース 失われたアーク《聖櫃》』(1981年)
で約40年前に共演した、ハリソン・フォードとキー・ホイ・クァンによる授賞式の舞台での再会のシーンは
(チラッとうつるスピルバーグ氏の表情含めて)
正に映画の感動の場面そのものにて、グッ😢とくるものがありました。
2023 Oscars: 'Everything' wins best picture, is everywhere at Oscars
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する音楽情報
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する音楽情報として
サントラ盤や
本作の音楽を担当された
”サン・ラックス(Son Lux)”
に関する情報について、以下にご紹介します。
作品情報「Everything Everywhere All at Once (Original Motion Picture Soundtrack) 」
以下のサイトで試聴することができます。
Everything Everywhere All at Once (Original Motion Picture Soundtrack) / Son Lux
出典:bandcamp.com URL:Everything Everywhere All at Once (Original Motion Picture Soundtrack) | Son Lux (bandcamp.com)
Everything Everywhere All at Once Soundtrack
出典:tunefind.com URL:Everything Everywhere All at Once Soundtrack Music - Complete Song List | Tunefind
全49曲はなかなかのボニュームですが
それぞれを楽曲として楽しむには、少々厳しい内容(爆)かもしれません。
Spotifyもバッチリ全曲upされてます。
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス”ジョン』の音楽を担当した”サン・ラックス(Son Lux)”について
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス”ジョン』の音楽を担当したのは、アメリカの音楽グループ”サン・ラックス(Son Lux)”です。
.@SonLux is the first band to receive a scoring nomination, credited as a band, since The Beatles won best original song score in 1971 for 'Let It Be.' https://t.co/8KC24n7JAe
— billboard (@billboard) February 15, 2023
”サン・ラックス”については
下記H.Pの内容によると
Son Lux — Official Website
出典:Son Lux URL:https://sonluxmusic.com/
創設者 Ryan Lott のソロ プロジェクトとして始まったプロジェクトが
2014年にイアン・チャン (Ian Chang) と ラフィーク・バーティア (Rafiq Bhatia) が加入してトリオに拡大。
トリオとして、 Brighter Wounds (2018) と 3 枚組アルバムTomorrowsを含む 6 つのスタジオアルバムをリリース済。
バンドは、ソウル、ヒップホップ、実験的な即興演奏を行ったりする活動を行っている。
といったグループのようです。
”サン・ラックス”は、これまでかなりのYouTube動画を製作しておりますが
それらの動画で彼らの作品を聴いていくと
何となくですが彼らの世界観がみえてきます。
楽曲自体も単純にPC上でつくりあげるのではなく、Live的な活動での表現も結構されております。
Son Lux — "Easy" with Woodkid (Live at Montreux Jazz Festival 2016)
先日のアカデミー賞でのパフォーマンスも、斬新で印象的な内容でした。
【NEWS】
デヴィッド・バーンとサン・ラックスが第95回アカデミー賞授賞式で最多ノミネート作品『Everywhere All at Once』サントラ収録曲「This Is a Life」を披露。実際の曲で歌っているMitskiに代わり、出演俳優のステファニー・スーがバーンとデュエットした。https://t.co/Nz2p9O3auk— TURN (@turntokyo) March 13, 2023
”サン・ラックス”の楽曲について、オヤジ(Robert)がいろいろ聴いた中で気に入ったのがこちらの楽曲です。
シンプルな歌詞が,静かにメロディに溶け込んでいく感じが、美しく表現されております。
Son Lux - No Fate Awaits Me ft. Faux Fix (Official Audio)
こちらのVは楽曲はともかく(爆)、表現の手法と音楽と映像の一体感が天才的でもあり凄い作品です。
Son Lux - Change Is Everything (Official Music Video)
ただ、”サン・ラックス”の楽曲については
突き抜けた明るさや、先ほどの曲のような分かりやすいメロディの曲は少なく
最近upされた曲でもある、以下の作品もどちらかというと哲学的というか、少し陰なイメージがあります。
Son Lux – “Undertow" (Official Video)
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス”ジョン』の監督であるダニエルズが
今回彼らを指名したのも、ご自身が表現しようとしている世界と、サン・ラックスの音楽の世界とに共通性があったためと想像しますが
その音楽から感じる新しい感覚と、映像との一体感を作り出す才能については
そのカオスの世界を表現するには十分魅力的な存在だったはずです。
エンドロールで流れていたこちらの楽曲も、劇場で鑑賞した時点ではほぼ感じませんでしたが、
彼らが、本作品の世界に大分歩み寄ったかたちでの創作物になっており、新たな道を開いた感じがします。
This Is A Life (Extended)
▼ 提供:株式会社レコチョク ▼
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する勝手なエバリュエーション
本作品に関する
"オヤジ(Robert)の勝手なクライテリア"
(【オヤジ(Robert)の勝手なクライテリア】はこちらのページに掲載)
によるエバリュエーションは
"A”
- A : また是非みたい作品
(個人的な理由(前回鑑賞時にあまり理解できてない/前回鑑賞時に途中寝てしまった/ しばらく見てなかったから) 含む)
となります。
理由は
以下のメンバーとのインタビューでも登場していた
オヤジ(Robert)も好きな作品でもある
映画『サマー・オブ・ソウル(あるいは、革命がテレビ放映されなかった時)』
の監督のクエストラブも既に15回も観たと言って、サン・ラックスの楽曲含めて絶賛していましたし
Everything Everywhere All At Once | Questlove & Son Lux Conversation | Official Clip | A24
多分まだ全然理解してない”最先端のカオス”についての学びも含めて復習するためです。
▼ Amazone.co.jp ▼
『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関するパンフレットの記憶
今回のパンフレットは
オヤジ(Robert)のように、作品に置いてきぼりにされた感のあるかたにとっては、必需品となる作品に仕上がっております。
構成的には、最近は少なめでもあるコラムについて
5人ものかたによる記事が掲載されているという異例の状態でしたが
オヤジ(Robert)的には、やはりこの作品の分かりにくさに対する
このパンフレット制作者の方々の(映画愛故の)解であると理解しました。
特に、ニヒリズム(虚無主義)という考え方についての内容を交えた解説は、本作の理解をかなり進めてくれました。
オヤジ(Robert)的に、このニヒリズム(虚無主義)に対して、これまでどう向き合った来たか?改めて考えた時には
やはり、師匠(浜省)のあの楽曲が頭の中で流れてきて・・・
もう遠い昔に腑に落ちて忘れていたテーマであることが想起されました。
君と歩いた道 浜田省吾
それから、音楽ライターの新谷洋子氏による
サン・ラックスについての内容や
本作の劇中歌に対するCDのライナーノーツ並みの解説に関しては、非常に興味深い内容で
今回サン・ラックスの音楽について、興味をもつきっかけにもなりました。
あと、残念ポイントとして
出演者のかたがたのインタビュー記事が無かったところがありますが
Web記事や先ほどご紹介した動画を含めて結構露出されているようですので
そちらの情報で十分かもしれませんね。
さらには、本パンフレットの冊子の「中とじ込み」のようなっていた部分で紹介されていた
沢山の画像(詳細は秘密)については、非常に遊び心ある演出でしたし
あらためて本作の映画の方の製作者の方々の編集作業のご苦労を感じました。
まとめ
今回は、映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する内容として
・映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する勝手な感想文
・映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関する音楽情報
・映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』に関するにパンフレットの記憶
などご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか?
この記事を読んで頂きましたみなさんも
最先端のカオスが楽しめる
映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』
是非、ご鑑賞してみてはいかがでしょうか?
-


関連記事映画界の巨匠スティーブン・スピルバーグの伝記的作品 映画『フェイブルマンズ』感想
UnsplashのAlex Steynが撮影した写真 スティーブン・スピルバーグの幼少期はどんな子供だったの?マサマサ 映画界の巨匠”スティーブン・スピルバーグ”監督が、自らの主に幼少~青年期を中心に ...